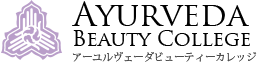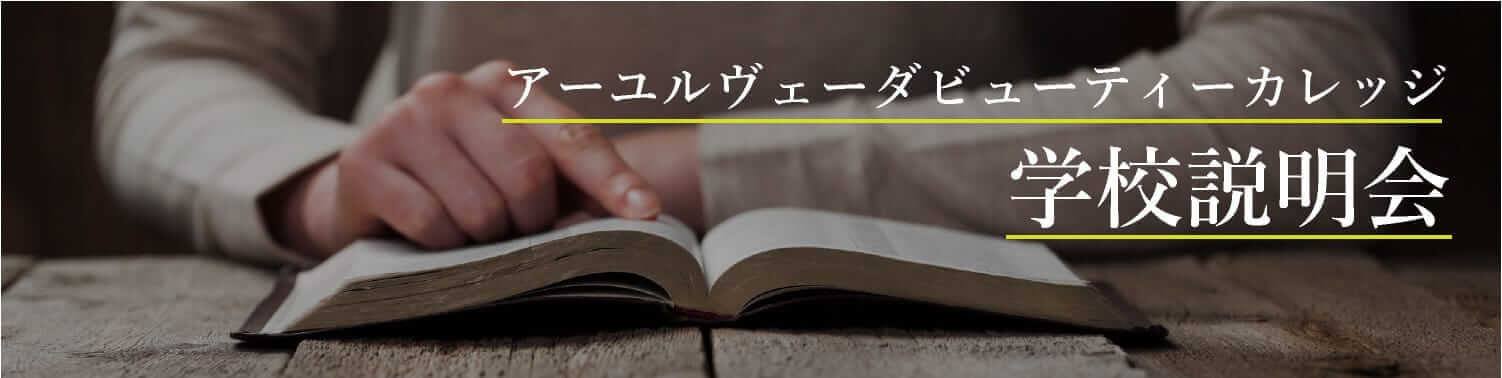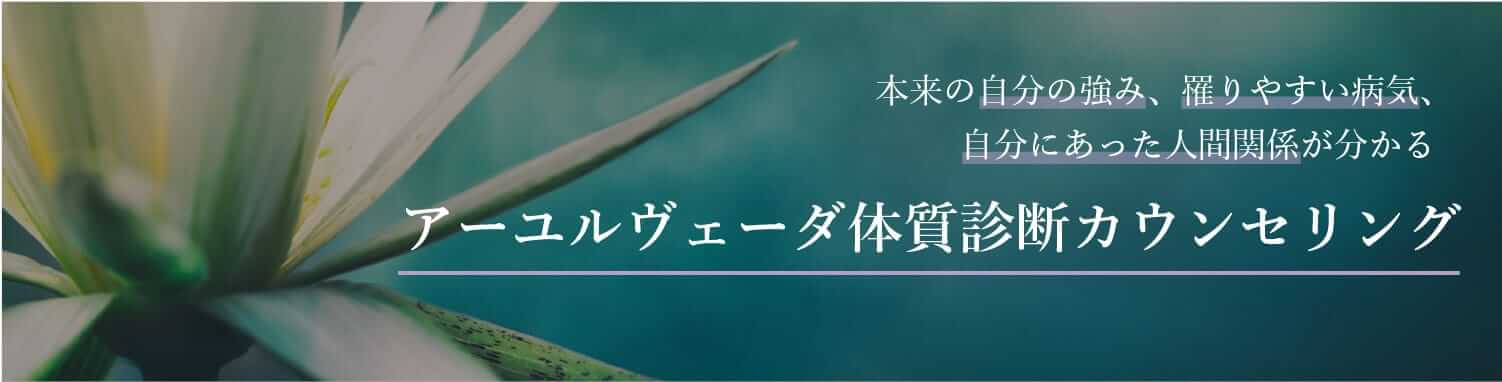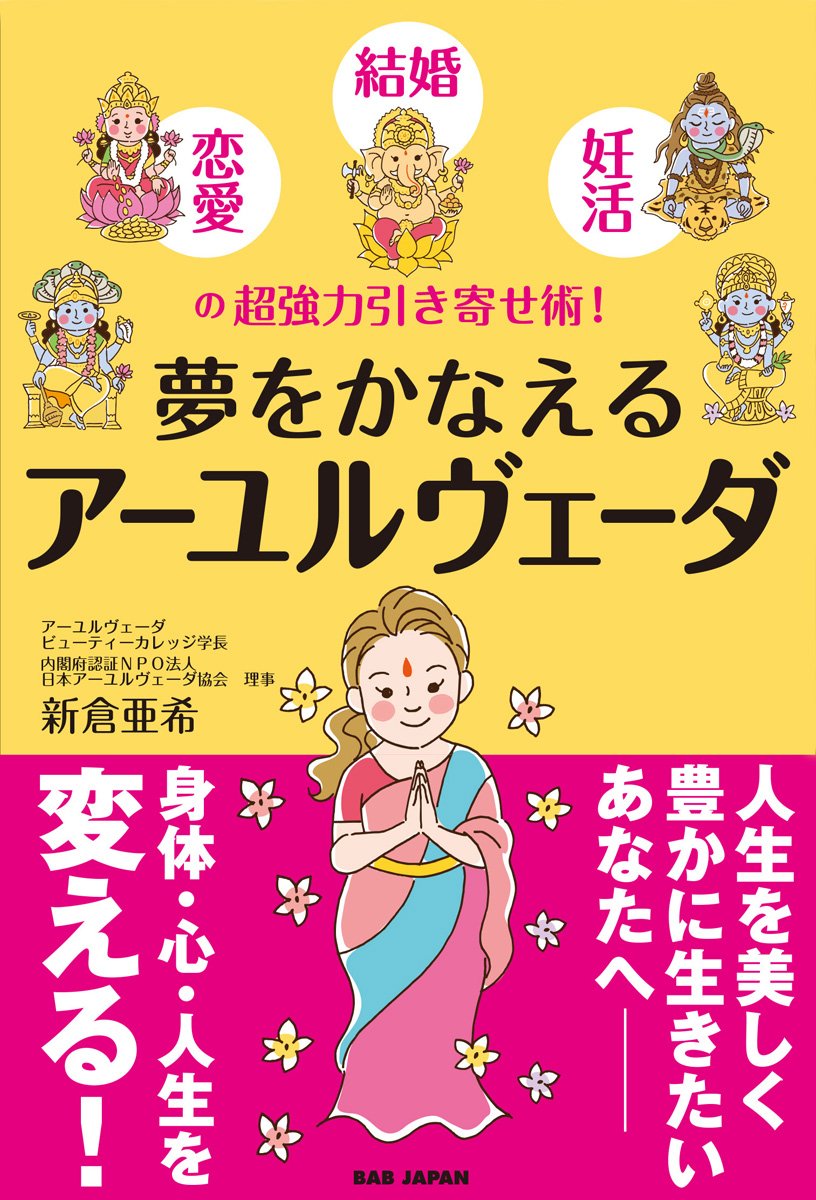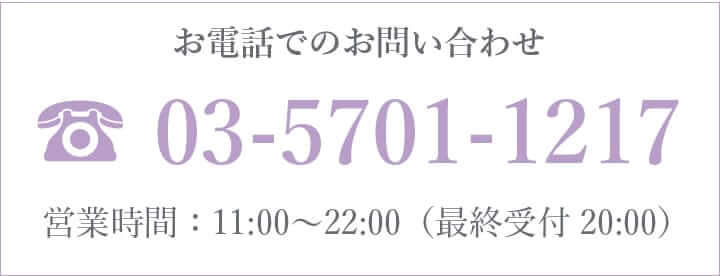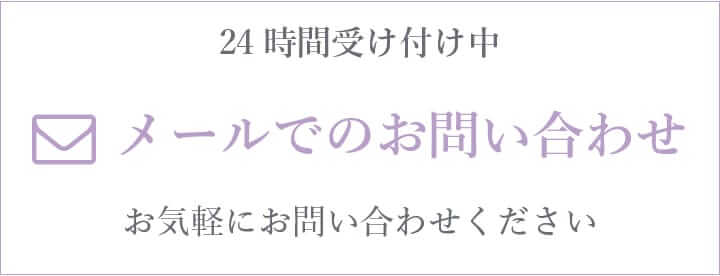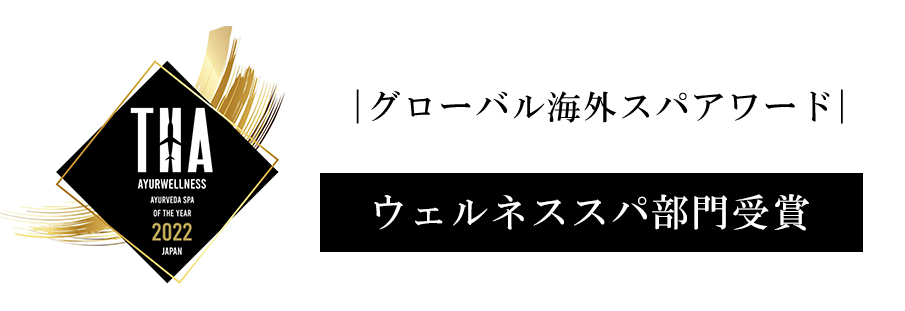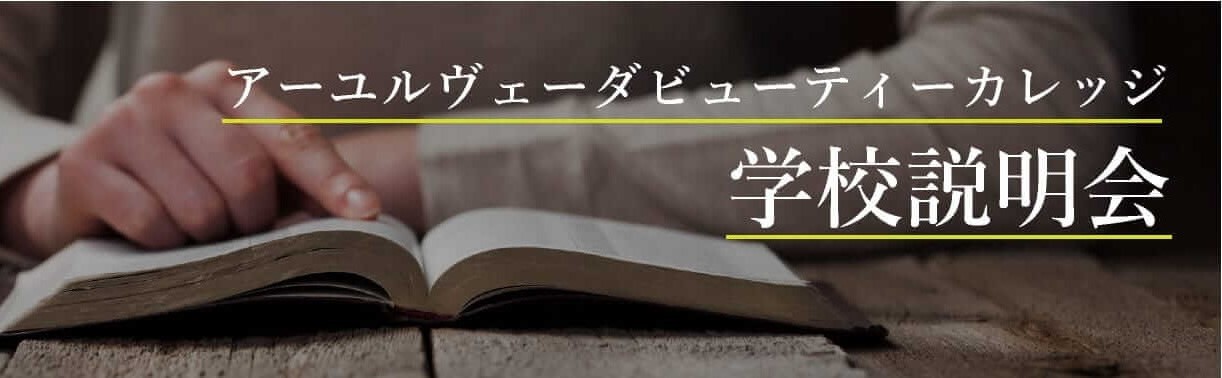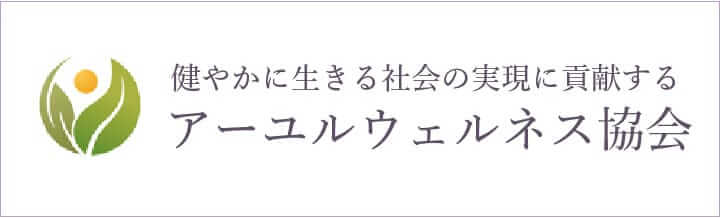2025.8.11 月曜日
最近急増する「起立性調節障害」をアーユルヴェーダで紐解く
中学生の10人に1人が抱える“見えない不調”を、アーユルヴェーダで紐解く
最近、日本の中学生の約10人に1人が起立性調節障害(OD)といわれています。
朝起きられない、立ち上がるとふらつく、動悸や頭痛がする——こうした症状は怠けや甘えではなく、自律神経や血流の調整機能がうまく働かないことから起こります。
アーユルヴェーダから見た「根本原因」
インド伝統医学アーユルヴェーダでは、体と心のバランスを3つのドーシャ(ヴァータ・ピッタ・カパ)でとらえます。
起立性調節障害は特にヴァータ(風のエネルギー)の乱れが深く関係していると考えられます。
• ヴァータは血流・神経伝達・循環を司る
• 睡眠不足、不規則な生活、冷たい飲食、過剰なスマホ・ゲーム時間で乱れやすい
• 成長期の体はエネルギー需要が高く、乱れが自律神経の不安定さにつながる
アーユルヴェーダ的アプローチ:体質と生活を整える
1. 生活リズムの安定
• 毎日同じ時間に起きて、同じ時間に寝る。特に6時前の起床が身体が自然の摂理で起きやすくオススメ。
• 朝はゆっくり体を起こし、朝日を浴びる
2. 温かく滋養のある食事
• 朝食を抜かず、温かいスープやおかゆからスタート
• 塩分と水分をしっかり摂る(ミネラル豊富な岩塩やハーブティー)
3. オススメハーブ
• ブラフミー(Brahmi)
「脳のハーブ」と呼ばれ、神経系を鎮静し、集中力・記憶力を高めます。ストレスや不安感を和らげ、睡眠の質も改善。血流や自律神経の働きを整える作用があり、起立性調節障害に伴う疲労感、めまい、立ちくらみにも有効とされています。
→ お茶、パウダー、オイルマッサージなどで活用可能。
• ジンジャー(Ginger)
体を温め、血行を促進。冷えや循環不良による立ちくらみに。
• 温かいセサミオイル
足裏や頭部マッサージで血流促進と神経の安定。特に就寝前が効果的。
4. 軽い運動と呼吸法
• ゆったりとしたヨガ、ストレッチ、深呼吸で循環を促す
• 過度な運動や夜更かしは避ける
まとめ
起立性調節障害は、単なる体調不良ではなく心と体のバランスの乱れが背景にあります。
アーユルヴェーダは「症状」だけでなく、その奥にある生活習慣・体質・心の状態を整えることを大切にします。
規則正しい生活、温かい食事、ハーブやオイルケアを通じて、少しずつ回復の土台を作っていきましょう。
沖縄の自然とアーユルヴェーダの叡智は、そのための強い味方になります。
ブラフミーハーブ詳細はこちら
https://ayurbeauty.thebase.in/items/21517773